大人の科学マガジン プラネタリウム専用電球ができるまでー後編ー「星空を生み出す職人の手仕事」
大人の科学マガジン 細渕電球特注版 ピンホール式プラネタリウム
細渕電球が作るプラネタリウム専用電球「GAKKEN-HOSOBUCHI」は、職人たちの繊細な手仕事によって作られている。前編の「継線」や「封止」に続き、後編では、いよいよ電球が完成するまでの工程へと進む。淡々と、ひたすら精確に、自分たちが積み重ねてきた時間と技術を電球に落とし込んでいく。ひとつひとつの作業に込められた職人の情熱が、どのようにプラネタリウム専用電球を作り上げるのか、その秘密に迫る。
【★前編の記事はこちら】
大人の科学マガジン プラネタリウム専用電球ができるまで
―前編― 「細渕電球の 100 年電球」

―排気― 電球に命を吹き込む
「この工程がうまくいかないと、電球は一瞬でダメになるんです。」
工房の壁際に設置された大型機械から、真空ポンプの作動音が響く。続く工程は「排気(はいき)」。これは、電球内の空気を抜き、特殊なガスを封入する作業だ。

▲この機械1台で、電球内部の空気抜き、余分な水分の蒸発、特殊ガスの封入までを行う。
まず、ガラス球は全長2mの大型機械へと運ばれ、真空ポンプで空気を抜かれる。空気が残っていると電球の耐久性が落ち、品質に大きく関わってしまうため、1個ずつ状態を確認しながら作業を進める。
排気が正しく行われたかを確認するために、職人はテスラコイルと呼ばれる高電圧を発生させる装置をガラス球につながったステム(ガラスのパイプ)にかざす。内部に空気が残っていると紫色に発光し、真空度が高いほど発光色は白く薄くなっていく。

▲テスラコイルをかざして、真空状態をチェックする。
高い真空状態を保っていることが確認できたら、次にガラス球は約400℃の炉で5分間加熱される。これにより、内部の水分が取り除かれ、より真空に近づく。その後、ガラス球の中に不活性ガスを封入する。不活性ガスで満たすことで、高温になるフィラメントの蒸発が抑えられて電球の寿命が延びるのだ。そして、電球に通電し、ひとつひとつ点灯を確認する。光が広がった瞬間、電球に命が宿る。

▲通電させて点灯チェックをする。
最後に行うのは密閉作業。職人は片手でガラスを回転させ、もう片方の手でバーナーを操る。炎の熱でガラスを徐々に焼き切り、ステムとガラス球の接続部分を密閉していく。正確な位置で切断するには、長年の経験と熟練の技が求められる作業だ。

▲バーナーを使ってステムを焼き切る。
―仕上げ― 精度を決める職人の技
排気を終えた電球は、次に口金を取り付ける「仕上げ」へと進む。口金は、電球をソケットにしっかりと固定し、安定した通電を可能にするパーツだ。まず、職人は口金の内部に専用の熱硬化接着剤を詰める。そして、電球から出た2本の電極線を1本は口金の底面に、もう一本は側面に引き出しながら、垂直に口金にはめ込む。


▲口金の内部に熱で硬化する接着剤を詰める。

▲電極線を引き出しながら口金に差し込んでいく。
その後、電球を炉で加熱し、口金とガラス球をしっかりと固定。余分な電極線をカットし、側面と底部にハンダづけをする。
こうして、細部まで職人の手で仕上げられた電球は、ついに最終工程へと進む。

▲口金の側面と底面に電極線をハンダづけをする。
―検品― 最高の電球だけが、星となる
最終工程は、電球の品質を徹底的にチェックする「検品」だ。
電球は2.5V、0.7~0.8Aの条件で点灯テストが行われる。職人たちは、光の強さ、均一性を細かく確認する。こうして、厳しい基準をクリアしたものだけが、プラネタリウム専用電球「GAKKEN-HOSOBUCHI」として出荷されるのだ。

▲出荷前に1個ずつ通電検査を行う。

▲完成したプラネタリウム専用電球「GAKKEN-HOSOBUCHI」。
工場長の思い
プラネタリウム専用電球「GAKKEN-HOSOBUCHI」は多くの職人の手によって作られている。継線、封止、排気など、それぞれの持場にいる職人が自分たちの役割を果たし、100年電球が生まれている。

▲細渕電球の職人を束ねる村田さん。
細渕電球株式会社の工場長である村田義勝(むらたよしかつ)さんは語る。「今回のフィラメントのような小さな寸法だと、機械では生産できません。職人がひとつひとつ、自分たちの目と手の感覚で作っていくしかないんですね。1個だけ、いいものを作ればいいわけじゃない。細渕電球が作った以上、みなさんの手元に届けられる電球はどれもが高品質であると言えないといけません。」
そう言い切るのは、自分たちが職人だからこその思いがあるからだ。
「自分が世の中に出せるものを作れたと思ったのは、始めてから5~10年くらい経ったころでしょうか。職人の世界には教科書が存在しないし、仮にやり方を頭でわかったとしても、そのように手が動かせるわけではありません。先輩たちの技を見て、仕事を仕込まれて、かれこれ30年間、職人をしています。
今でも失敗をするし、いつだって体調万全というわけにはいきません。それでも、私たちはいい電球を作らないといけません。それが仕事だからです。これはもう、技とか経験をこえて、恥ずかしいものを見せられないと考える職人の意地みたいなものですね。」

▲機械を使わずに、バーナーを使って手先の感覚だけで「封止」をしている。
村田さんは「GAKKEN-HOSOBUCHI」電球で少しだけ期待していることがある。
「電球は光ってなんぼ、みたいなところがあるので、日常生活で電球それ自体を眺めることはふつうないですよね。でも、今回読者のみなさんの何人かが、これだけの小さなフィラメントを人の手で作っているってすごい、そう思ってくれたら、わたしたち職人は本当にうれしいですね。」
細渕電球が生み出す「100年電球」。それは、職人たちの技術の結晶であり、長い歴史の中で磨かれたもの。しかし、それは過去のものではない。村田さんは
「この技術を守るだけじゃなく、この技術を活かして、新しいものにも挑戦していきたい。職人はあきらめないで続けること、それが一番大事。」と語る。
細渕電球の技術は、決して歩みを止めることなく、未来へとつながっていく。そして今、この電球が生み出す光が、プラネタリウムの星空となり、すべての人の心を、そっと照らしている。

文:編集部 写真:大野真人
【★前編の記事はこちら】
大人の科学マガジン プラネタリウム専用電球ができるまで―前編― 「細渕電球の 100 年電球」
商品について

■書名:『【2,000個以上予約受注で発売決定】【Amazon.co.jp限定】大人の科学マガジン 細渕電球特注版 ピンホール式プラネタリウム』
■監修:大平貴之 電球製造:細渕電球株式会社
■編:大人の科学マガジン編集部
■発行:Gakken
■発売日:2025年7月22日
■定価:12,100円(税込)
本書を予約する(Amazon)※本商品は2,000件以上の受注で発売が決定する、条件付き予約受注生産販売の商品です。生産数量は最大3,000個を予定しています。
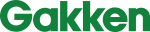







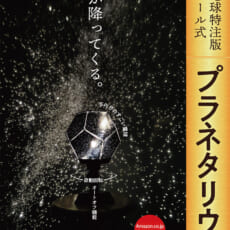






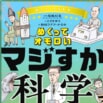
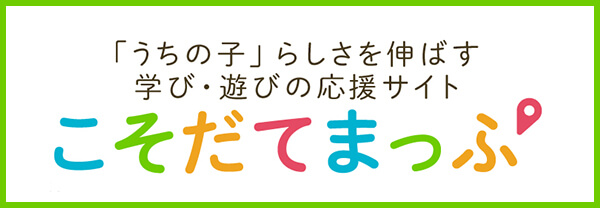



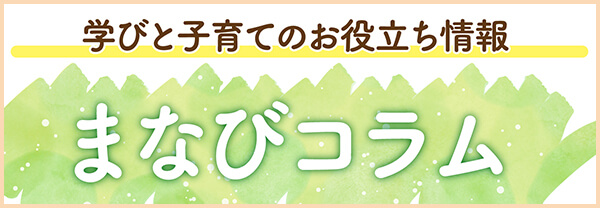
 ページトップへ
ページトップへ