第2回 芸術作品って、そこに何かが“有る”ことを表現しているものと、そこに何かが“無い”ことを表現しているものの二種類あると思うんです(道尾)
道尾秀介(作家)対談 「Jam Session」



道尾:僕はとにかく河瀬監督の映画の大ファンなんです。ドキュメンタリー作品も含めて。あ、先ほど話していた『萌の朱雀』の小説版(幻冬舎文庫)も大好きですが。
河瀨:恐縮です(笑)。
道尾:僕は映画についてはまったく詳しくないんですけど、すごく信頼している編集者が、あるとき『沙羅双樹』(2003年)を薦めてくれたんですね。それを観て、「こんな映画があったのか!」とびっくりしました。本当に初めて観るタイプの作品で、それから『萌の朱雀』をDVDで観て、手に入る作品は全部観ています。「好きな映画監督は?」と聞かれたら、まず「河瀨直美さんです」と答えているくらいで。

河瀨:本当ですか! ありがとうございます。今回の撮影は奄美(大島)だったんです。道尾さんの『月と蟹』は、月とか、海の感じがすごく奄美っぽいんです。
道尾:そうなんですか。
河瀨:ええ。2ケ月半、奄美に滞在していたんですが、この本は私のベッドのヘッドボードにずっと立っていましたからね。いっしょにお泊りしてました(笑)。
道尾:ありがたいですね(笑)。
河瀨:道尾さんは「映像にできない感じのことを小説にするようにしている」作家だと伺っていたので、そういうことを意識しながら読みました。でも私の映画は、絵にならないものを画にしてるつもりでなんですよ。だから、読みながら「この小説は全部を映像化したい」と感じました。1行の文章に隠れているものってありますよね。シナリオを書くときは、それをみんなで一生懸命捕まえていくんです。今回も、奄美でそんなことをずっとやっていました。撮影自体は1ヶ月だったんだけど、準備のためにその前からみんなで共同生活をしたんですね。
映像というのは文章に比べると具体的なものなんです。たとえば、「海」という言葉から受け取るものはそれぞれ違いますから、イメージが広がりやすい。でも映画の場合、撮ったらその映像しかない。そこから観た人に記憶を呼び返してもらうためには、生きた風景を撮らなければいけないんです。それには、映らないはずの心を投影する作業が必要です。だから『月と蟹』を読んだときも、文章には表現されていない、主人公たちの感情、感覚というものがビシバシ伝わってくる気がしました。
道尾:僕は、『沙羅双樹』を観たときに、まさに同じようなことを感じたんです。他の河瀬作品でもそうなんですけど、そこに映っているものがすべてじゃない、と教えられるあの感覚。そういう映画を観たのは初めてだったんですよ。芸術作品って、そこに何かが“有る”ことを表現しているものと、そこに何かが“無い”ことを表現しているものの二種類あると思うんです。例えば写真などは、“無い”ということを作品にしやすいメディアですよね。でも、映画ではすごく難しいのではないかと。
河瀨:なるほど。
もくじ
大事なことは映画の中でいかに時間を描くかということじゃないか、と最近私は思っています(河瀨)

道尾:たとえば「星はなぜきれいなんですか?」と聞かれて、普通の人は「キラキラ瞬いているし、真っ暗な夜空に光が浮かんでいるから美しい」といった答え方をすると思うんです。でも、河瀨さんはたぶん、「星と自分の間に何も無いから」という発想をされるのではないかと。たとえば、星をどうやってきれいに見せるかというとき、普通の人は、星そのものの光量を上げたり、数を増やしたりすると思うんですけど、河瀨さんはたぶん、星とカメラの間にあるものを徹底的に取り除いて空気をきれいにして、星を光らせるんじゃないかな、と。映画を観ているとそういう風に思います。『追臆のダンス』などは、まさにそれだなぁと思いましたね(2002年。写真評論家・西井一夫が死去するまでの日々を撮ったドキュメンタリー)。
河瀨:実は、明日(11月25日)がその方のご命日なんです。13回忌だから12年前の今日は、私は彼のいたホスピスで時間を過ごしていました。お話があったのはその2ケ月くらい前で、そこからすべての仕事をキャンセルして通い始めたんです。彼のために何かをしようと思ってもどうにもならない。思いとしては、亡くなっていく人を撮っているのではなく、今在るものを撮っているのみでした。カメラを向けている瞬間に彼はひどく咳き込んだりもします。そこは本来ならばカメラを捨てて介護する場面なのでしょうけど、私は「最後までちゃんと撮れ」って本人に言われているので、絶対に撮影を止めてはいけない。そういう自分でそこにいるってことなんですね。だから際どい自分が二人、そこにはいました。彼との時間を見つめている自分と、彼が病室に帰ってしまったあとに、ちょうど落葉の季節で、それがアスファルトの上に舞い落ちている。その葉を踏んづけたりしている足元を撮る自分と。
道尾:ああ。

河瀨:映画を撮るときには、監督であり表現者なので、作為的になりますよね。私がドキュメンタリーから出発しているからかもしれないのですが、物事をコントロールしようとしても限りがあるということを感じます。そうではなくて、そこにあるものに自分が沿うて行くというだけでも十分にドラマチックで、人生は素晴らしい。
道尾:よくわかります。
河瀨:道尾さんがおっしゃったこととつながるかもしれないんですけど、何かを捉えていくということよりも、本当に何を捨てるのかということに一生懸命心を沿わせている感じです。たくさんのものがある中で、何を捨てるのか。それで残ってくるものだけが、永遠になるという、そんな気がしますね。

道尾:映画だと、最後に編集作業というものがあるじゃないですか。たとえば、ハリウッド映画のDVDだと、「特典映像」にカットされた部分が入っていたりしますよね。あれを観ると、捨てた映像の中にものすごく金のかかっていそうなものもあって、こんなに大金をつぎ込んだものを、全体のバランスを考えて捨てているのか、と驚きます。いっぽうで、河瀨さんの映画はお金がすごくかかっているってわけじゃないですよね。ハリウッド映画に比べてですけど。
河瀨:そのとおり(笑)。
道尾:それは素人目にもわかるんですけど。じゃあ何がかかってるかっていったら、人の気持ちがそこに全部入り込んでいると思うわけですよ。それこそ監督のお気持ちも、出演された方々のお気持ちも。それを捨てていくのは、お金のかかったシーンを捨てるより辛いことだと思うんですよね。
河瀨:今回、85時間も回しちゃったんです(笑)。映画って、なんぼ多くても2~3時間じゃないですか。でも、たとえば80歳の人の人生だって2時間で描かなければいけない。大事なことは映画の中でいかに時間を描くかということじゃないか、と最近私は思っています。今回は、奄美におけるひと夏の物語なんですが、その中で時間を描くというのは、人の心の移り変わりを描くってことだし、そこに存在していたことが存在しなくなるってことなんです。そういう積み重ねをしてきたものを、今から苦渋の選択で切っていくわけです。実際には編集が撮影の倍かかるんですよ、思いも時間も。どんないい素材を撮ってきても、下手な編集をしてしまったら、時間は流れないし、描けない。つまりは人の感情をちゃんと流せないんです。説明する時間じゃなくて、感覚的に人の心に宿っていく時間。そういうものを活かすのに、編集はとても大切な作業です。
道尾:そうなんでしょうね。
一文字でも短ければ短いほどいい、余計なものがないほうがいいんで(道尾)

河瀨:『殯の森』以降、私はずっとフランス人のスタッフと編集をやっています。フランス人は日本語わからないじゃないですか。わからないからこそ映像のテンポで編集してくれるんですよ。それにすごく触発されます。言葉の意味とか、場面の展開だけではなくて、映像のリズムなんです。時間は流れているから感覚は流れていて、意味はそっちのほうがダイレクトに伝わる。先日から85時間の映像を送って、今観てもらっている状態なんです。
道尾:日本人とフランス人の違いというのはおもしろいですね。
河瀨:フランス、特にゴダールの作品などに特徴的なのはジャンプカットが普通にあるんですね。その点、日本人って丁寧なんですよ。右に歩いたら、右に何があるかを絶対に見せなきゃいけない。でも、別に右に曲がった後の何かを見せなくても、そこの感覚を感じさせればいいだけなんですよね。歩いてきたら、ちゃんと一度立ち止まらないといけないとか。でも、それをポンと飛ばして、次に座ったカットになっても、「あ、歩いてきたんだ」ってわかる。たとえばその方が急いでいる感じが伝わったりするかもしれない。日本人の編集者に言わせると、「そこまで歩いて行った意味がわからないじゃないか」って感じになる。だけどリズムで考えれば、「急いで歩いて行ったってことが伝わればいいんじゃない?」っていうことなんです。
道尾:観終わった後に、観客がその家の間取りを描けなくてもべつに問題ないわけですよね。
河瀨:そうそう。ひとつの映画を観て、すべてのカット順を描ける人っていないです。それよりもトータルの流れ、リズムが大事かなぁって思います。

道尾:文章でも基本的には、全部説明することの無粋さというのはあります。文体を損なわない限り、一文字でも短ければ短いほどいい。読者の想像の割合を高めるために、余計なものはないほうがいい。ただ、僕の作品に限らず、そうやって密度を高めたものは「わからない」と言われがちです。なぜなら説明していないので。僕も作家のはしくれですから、わかりやすいもの、わかりにくいもの、もちろんどちらも書けます。その、どっちを書くかっていうときに、出版社には申し訳ないのですけど、どうしても売り上げ部数より密度を選んじゃうことが多いんですが(笑)。
河瀨:ああ(笑)。
道尾:わかりやすいものだって書いているんですよ、何冊か。そういうものも好きですし、ときには書きたいですから。そっちは、やっぱりすごく売れるんです(笑)。部数が、まったく変わってくるんですよ。
司会・構成/杉江松恋 撮影/干川修
作品紹介

月と蟹
海辺の町、小学校の慎一と春也はヤドカリを神様に見立てた願い事遊びを考え出す。無邪気な儀式ごっこはいつしか切実な祈りに変わり、母のない少女・鳴海を加えた三人の関係も揺らいでゆく。「大人になるのって、ほんと難しいよね」-誰もが通る”子供時代の終わり”が鮮やかに胸に蘇る長編。直木賞受賞。
プロフィール
河瀨 直美
映像作家。生まれ育った奈良で映画を撮り続ける。1997年、初の劇映画「萌の朱雀」でカンヌ国際映画祭カメラドール(新人監督賞)を史上最年少で受賞し、鮮烈なデビューを果たす。その後、2007年に「殯の森」で同映画祭にてグランプリ受賞。2014年カンヌ映画祭では日本人監督として初めて審査員を務めた。2010年から2年に1度開く「なら国際映画祭」ではエグゼクティブディレクターとして奔走する。現在、最新作「2つ目の窓」(2014年夏公開)を製作中。
道尾 秀介
1975年東京都出身。2004年、「背の眼」でホラーサスペンス大賞特別賞を受賞し、作家としてデビュー。2007年「シャドウ」で本格ミステリ大賞、2009年「カラスの親指」で日本推理作家協会賞、2010年「龍神の雨」で大藪春彦賞、「光媒の花」で山本周五郎賞を受賞。2011年「月と蟹」で直木賞を受賞。近著に「カササギたちの四季」「水の柩」「光」「ノエル」「笑うハーレキン」などがある。
バックナンバー
- 第1回 普段の人間関係の中の立ち入らないようなところとか、そういうものが克明に出ている感じを『月と蟹』からは受けました(河瀨)
- 第3回 この人が本気で人を愛することができる人か、というのも表現から一目瞭然ですね(道尾)
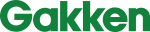

















 ページトップへ
ページトップへ