第2回 一番のルーツはクラシックと童謡ですね。普通の『ちょうちょ』とか『ぞうさん』とか。そういうものにルーツがあります。(style-3! 髙嶋)
道尾秀介(作家)対談 「Jam Session」


道尾:あの、いろいろお聞きしたいことがあって、今日は珍しくメモを作ってきたんです。対談で、こんなの用意したことないんですけど(笑)。ここからいくつかお聞きしてもいいですか? 僕はミステリー風味の小説を書くことが多いので、ミステリー小説はできるだけ読まないようにしているんですね。ミステリーを読んでミステリーを書いても面白いものができない気がして。もちろんこれは独自のやり方で、正しいかどうかはわかりませんが。そういう意味でも、style-3!さんのクリエイティビティーのソースはどの辺から来るのかにすごく興味があって。

高嶋:作曲しているのは僕なんですけど、一番のルーツはクラシックと童謡ですね。普通の『ちょうちょ』とか『ぞうさん』とか。そういうものにルーツがあります。もちろん、今流行ってるリズムとか、コード進行とかは取り入れるんですけど、一番のフレーズやドレミファソラシドを考えるときは、口ずさみやすいことを重視します。源泉は、子供のころに聞いた童謡とかクラシックとか、それこそアニメの曲とか。そういうのが多いですね。体にストンって入っちゃってるものなので、そこからロックを勉強しようと、ジャズを勉強しようと、もう意識があるかないかのころから聴いていたわけですから。そこがやっぱりルーツですね。
道尾:ああ、なるほど。style-3!さんのメロディーが覚えやすかったり、聴きやすかったり、耳に離れなかったりする理由はそれなのかもしれませんね。以前、作曲家の小林亜星さんとお酒をご一緒しているときに伺ったんですが、たとえばギターを弾きながら曲を作っちゃダメだとおっしゃるんです。そうするとギターが無いと聴けない曲になってしまうからと。本当にいい曲というのは、メロディーだけを口ずさんで楽しめる曲だ、っていう自論をお持ちなんですね。確かに亜星さんの作られた曲には、誰でも知っていて、誰でも口ずさめる曲がたくさんありますよね。
小説を書くときには、いつも二つのことが頭の中をよぎるんです。一つは、ストーリーラインを口で説明できるようではダメだ、という考えで、リニア(単純)なものをつくることに対する警戒心が常に働いています。でも逆に、たとえばメロディーを記憶するように、頭の中にストーリーを入れて持ち運べて、そしてふとした時に思い出してもらえる、というのも素晴らしいことだという考えがあるんです。小説を書くときにはいつも、その二つの気持ちのせめぎ合いになります。長編と短編で書き分けてみたりもしてるのですが。

高嶋:僕も自分で作った音を聴きながら街を歩いてみて、「あ、コレちょっと変だな」って思って、修正することがあります。そういう口ずさみやすさというのも大事ですけど、逆に、音楽の形として新しいものも追求したいという気持ちもある。そうするとちょっと冒険もしたくなって、今まで誰も思いつかなかったような要素を曲に入れてみるんですね。そういう実験の連続です。聴きやすいけど飽きちゃダメだし、仕掛けをやりすぎても音楽として響かない。そのバランスがなかなか難しいです。
道尾:それもちょうどお聞きしたかったことなんです。一番最近ライブで聴かせていただいた「竜迅」という新曲、あれはものすごく冒険していますよね。「冒険」の反意語は「安定」だと思うんですが、バランスを知らないとアンバランスなものがつくれないように、安定を知らないと冒険はできない。「竜迅」を聴いたとき、安定を熟知した上で「ちゃんと冒険してるな」というのが、曲から伝わってきました。それは僕自身が心がけていることなんです。きちんとしたものが書けないと、傾(かぶ)いてものは書けない。たとえばピカソの若い頃の絵なんて、もう写真のように精密に描けていますよね。本物そっくりに描ける力を完璧に身に着けてから、ピカソは抽象絵画を描き始めた。そういった事実をいつも忘れないよう気を付けています。
高嶋:曲を書いてるときはすごい集中するので、いろんなフレーズが浮かんでくるんです。そういうときに何を選択の基準にするかというと、たとえば「竜迅」だったら、「竜迅」っていう旗を立てて、そこから届く範囲内で冒険しまくろう、っていうことなんです。
もくじ
誰かがいなくなってしまった圧倒的な悲しみを表すには「いるとき」の圧倒的な愛情とか、暖かさとか、愛おしさを先に書けるようにならないと、亡くなった後は書けないんです。(道尾)
道尾:音楽の曲名は、小説で言うと本のタイトルですよね。style-3!さんの曲は基本的にインストゥルメンタルですが、言葉がないものに対して、言葉のタイトルがついている。それってたとえば、タイトルを違う言葉に変えたら、曲自体も違うように聴こえてしまうわけですよね、おそらく。そのあたり、タイトルをつけることの重要さを感じます。
僕の本でいうと、『光』はそれほど迷いがなかったんです。これはタイトルがテーマそのものを表していて、読み始めからおぼろげな「何か」が見えていて、その「何か」の色が変わっていき、最後にはその「何か」を読者に受け渡す。登場人物たちのあいだでも、「何か」の受け渡しは行われている。その「何か」をどう呼ぶかと考えたとき、もう「光」という言葉しか考えられなかった。他の『向日葵の咲かない夏』、『シャドウ』、『片眼の猿』、『カラスの親指』、『球体の蛇』、『光媒の花』、『月と蟹』、『鏡の花』といった作品は、最後まで読み終えて初めてタイトルの意味がわかるという構造で、『ラットマン』や『ソロモンの犬』、『カササギたちの四季』などは、全編を通じて通奏底音のようにタイトルが鳴っている作品なんです。『龍神の雨』や『水の柩』や『ノエル』のように、読み進めるに従ってタイトルの意味が変わっていくタイプのものもあれば、『鬼の跫音』などは、ある瞬間に不意打ちでタイトルに意味づけがなされるようになっています。小説は、そういったタイトルの使い方ができるんですが、曲の場合はどうなのでしょう。いつも、タイトルを付けてから曲を作られているんですか?

高嶋:そういうときもありますが、メロを少し変えたところで「こっちのほうがタイトルとして正しいな」っていうときもあります。その「竜迅」という曲ですが、自分の中で「神」っていう字は使えないんですよ、おこがましくて。最終的に「竜迅」になったんですけど、迅速の迅なので、竜が駆け上るようなイメージがやはりこの曲に合うな、って思いました。そこからはいろんなフレーズ浮かんでも、「これは『竜迅』じゃないから」とメモをして別のところに置いておく。そういう風な感じで僕はタイトルを使ってますね。そういうイメージ中で、どこまで竜が駆け上がるイメージで、どこまで攻められるか、音楽的にアプローチできるかっていう冒険はやっていますね。
道尾:やっぱり、きちんとしたセオリーがあるんですね。ただ冒険してるわけじゃない。
高嶋:そう。好きに作るとしっちゃかめっちゃかになってしまいます。ましてや歌詞がないバンドなので。そこが一番重要ですね、作るときは。

道尾:前回、映画監督の河瀨直美さんと対談させてもらったときに、芸術作品には二つあって、それは何かが「有る」ことを表している作品と、何かが「無い」ことを表している作品だという話をしたんです。たとえば写真であれば、そこの、ただの壁を撮った作品があるとする。それは、何かが「無い」芸術作品ですよね。「何故こんなところを撮ったんだろう、何かが欠けている」という不安感を煽ることもできる。そういう話をしていたんですが、やはり何かが「有る」ことを完璧に表せる腕がないと、「無い」ことは絶対に表現できない。小説でも、誰かがいなくなってしまった圧倒的な悲しみを表すには、「いる」ときの圧倒的な愛情や、暖かさや、愛おしさを書けるようにならないと、亡くなった後の不在間は書けないんです。
高嶋:なるほど。
読んでくれる人がたくさんいてくださって、それぞれの心の奥の部分に触れることができるツールなんだな、ということを読みながら思いました(style-3)
道尾:演奏という面からもお聞きしたいのですが、アレンジのアイデアというのは、作曲者である髙嶋さんから五線譜の状態で渡されることが多いんですか?

長澤:五線で、「ここはこういう風に弾いてね」って指定されることもありますし、コードで来ることもありますね。弾いてもらいたいメロディーがちゃんと出来上がった状態で渡されることもあります。曲によって違いますよね。今、英輔が言っていたこととリンクする部分があるんですけど。僕にも自分の中で抜けない音楽っていうのはあって、そういったところを何となく音にすることもあります。コントラバスという楽器は演奏の一番低いところを支えるという役割でもありますし、今までクラシックをやっていたこともあって、冒険と安定といったら、正直、安定のほうを強く打ち出しちゃう人間かもしれない。
道尾:ベースラインですからね。そこで冒険しちゃうと、聴いていてすごく落ち着かない音楽になってしまう気がします。
長澤:まあ、冒険しないといけない部分もあるんでしょうけど、自分の中から抜け切れないというのが、課題といえば課題ですね。
道尾:そういう音楽っていうのは実際あるんですか? ベースラインが冒険してる曲って……。

長澤:自由にやるという意味ではジャズとかでしょうね。でも僕はジャズが不得手なもので。
道尾:でも、ライブではかなり冒険してますよね。ライブの長澤さんのパフォーマンスが僕はホントに好きで。
長澤:でも、基本は手拍子してるだけですよ(笑)
道尾:インストのバンドなのに、結構長い時間、楽器を弾いてないときもありますよね、客席を盛り上げるために。ベースを置きっぱなしにして、ステージを右へ左へ動いて拍手を煽ったり(笑)。そのおかげもあって、いつもすごい一体感ですよね、あのライブ。
長澤:じゃあ、今度からは手拍子だけでいきます。
道尾:それじゃまずいですよ(笑)。小説にはライブがないじゃないですか。モノとして出版されて、人がそれを読んでいるところは、まず著者は見ることができない。最後の一行を読み終えたときにどんな顔をするのか、本当は見てみたいんですけど、絶対にできないんですよね。ライブは、それが毎回できるので羨ましいと思うときもあります。
長澤:でも小説は小説でいいことがある。本当に無の状態からできて自由度が高いなって。読んでくれる人がたくさんいてくださって、それぞれの心の奥の部分に触れることができるツールなんだな、ということを読みながら思いました。
道尾:はい。僕はそう信じてるから小説書いているんだと思います。他の才能がなかったというのもありますけど、どんな表現手段よりも人の心を動かせるし、きれいな景色を描けると思っているからこそ、小説を書いてるんです。

長澤:音は強弱やニュアンスは伝えやすいですけど、文字だけで人に伝えられるというのはすごいことだと思います。
道尾:フィジカルなものが小説にはまったくないので、そこが音楽とは大きく違うところですよね。たとえば以前に長澤さん出演されていたテレビ番組で、コントラバスの魅力について「身体に響いてくる低音が癖になる」というようなことを言っていましたが、そういったものは小説にはありません。字でしか伝えられないというのは、もちろんデメリットとは思いたくはないですけど、やっぱり難しい面もあります。
長澤:いや、でもそれであれだけのものを書けるっていうのは、僕は正直羨ましいです。僕自身が日本語そんなに得意じゃないので(笑)
道尾:いやいや(笑)。そういえば堀江さんは子供の頃から読書がお好きなんですよね。
堀江:はい。図書館が近かったっていうのもあるんですけど、一人の作品を読むと「この作者はどういう人なんだろう?」って思って、同じ人のをバーッと読む癖があるんです。小っちゃいころから、いろいろ読んでましたね。

道尾:さっきの、アレンジのお話を聞かせていただいていいですか?
堀江: そうですね。基本はバイオリン譜の一段譜が渡されて「それじゃ、やってみよう」ってことで三人でせーので弾いてみる、みたいなのが最初です。それを何回かやって、それが英輔くんが自分の感覚と違ったら、「ここは実はこうなんだよね」とか話しながらやっていく感じですかね。
道尾:たとえば、『光』の最終章で思い浮かぶ「夢のあと」という曲がありますが、あれはピアノのソロの曲ですよね?
堀江:あれは、バイオリンではなくて、ピアノでやってほしいっていうことでした。メロディーは書いてあって、左手はコードで好きにやるみたいな感じです。「崩し崩し好きに弾いていいよ」みたいなことは言われてたんですけど、あれだけ特殊かもしれないです。初めてピアノ用に作ってきてくれたものなので。
小説はもしかすると、音楽に例えるとインストゥルメンタルなんじゃないかって気もするんですね(道尾)

道尾:そうだ、コード進行の件でお話ししたいことがあったんですよ。ギター片手に「いつもいっしょ」(style-3!唯一の合唱曲)のコードを調べてみて、面白いことに気づいたんですよね。これ、勝手にコピーしてみたんですけど、ちょっと鳴らしてみていいですか? (iPadでコードを演奏する)ここのAメジャーがすごく悲しく響くんですよね。でも、メジャーコード(明るい響きのコード)なんです。
高嶋:そうです。
道尾:メジャーコードなのに、前後の関係で、悲しく響く。これ、前後なしで弾くとこんな風に(Aメジャーを単独で演奏)、明るい響き以外の何物でもないですよね。コードと曲の関係って、連作短編集に似ていると思うんです。この『光』もそうで、主人公たちがとても馬鹿馬鹿しいことをやっている章があって、そこを単独で読むと著者のくせに思わず笑ってしまうんだけど、一冊の本として思い出すと、同じ章がとても悲しく感じられたりする。連作短編集というのは、コード進行みたいだなって思います。それともう一つ、小説は文字ばかりで構成されているにもかかわらず、音楽に例えるとインストゥルメンタルなんじゃないかって気もするんですね。コードによって、または裏で打たれてるベースラインによって、内容が違って聴こえてしまう。

高嶋:「いつもいっしょ」(style-3!唯一の合唱曲)は、実際にあった話というか、ご本人から依頼を受けて作った曲なんです。交通事故で障害を持たれて、若くしてお亡くなりになってしまったお子さんがいらしたお母さんと、その友達の気持ちを描いている。その頃の懐かしい、楽しい気持ちもありつつ、少し切ない、お別れがいつかあるよ、という感覚もあります。でも、気持ちはいつもいっしょだよ、というようなことでひとつひとつコードは配置していきました。
道尾:ああ、なるほど。あのAメジャーが悲しく響くのは、そのためでもあるんですね。腑に落ちることばかりです。お聞きできてよかった。
高嶋:「いつもいっしょ」(style-3!唯一の合唱曲)の詞はまじまじと見ると恥ずかしいものがあるんですけど。
道尾:いえ、この歌詞、すごく好きですよ。
高嶋:ああ、ホントですか。うれしいですね。
道尾:このへんも童謡の影響があるのか、とてもストレートですよね。回りくどい言い方をしていなくて。
司会・構成/杉江松恋 撮影/干川修
作品紹介

光
真っ赤に染まった小川の水。湖から魚がいなくなった本当の理由と、人魚伝説。洞窟の中、不意に襲いかかる怪異。ホタルを大切な人にもう一度見せること。去っていく友人にどうしても贈り物がしたかったこと。誰にも言ってない将来の夢と決死の大冒険ーー小学四年生。世界は果てしなかったが、私たちは無謀だった。どこまでも歩いて行けると思っていた。
プロフィール
style-3!
2004年結成。高嶋英輔(バイオリン)、長澤伴彦(コントラバス)、堀江沙知(ピアノ)の3人からなるポップインストユニット。熱いラテン調のものから明るいポップなもの、バラードまであらゆるジャンルを取り入れ、型にとらわれない楽曲で、数々のコンテストでグランプリを受賞している実力派。
道尾 秀介
1975年東京都出身。2004年、「背の眼」でホラーサスペンス大賞特別賞を受賞し、作家としてデビュー。2007年「シャドウ」で本格ミステリ大賞、2009年「カラスの親指」で日本推理作家協会賞、2010年「龍神の雨」で大藪春彦賞、「光媒の花」で山本周五郎賞を受賞。2011年「月と蟹」で直木賞を受賞。近著に「カササギたちの四季」「水の柩」「光」「ノエル」「笑うハーレキン」などがある。
バックナンバー
- 第1回 出てくるものが全部無駄なく、計ったように、でも無理のない自然の流れのままで出てくるのが「すげえなあ」と思いました。(style-3! 髙嶋)
- 第3回 もっとひと括りに言ってしまえば。声も音楽ですし。そういう意味合いで、自由に表現しちゃえばいいのかなあと思って。(style-3! 髙嶋)
- 第4回 小説はもしかすると、音楽に例えるとインストゥルメンタルなんじゃないかって気もするんですね。(道尾)
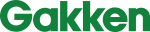

















 ページトップへ
ページトップへ