

序文(プロローグ)は、物語全体を象徴するシーンがいい。なおかつ、普遍性、永遠性を感じさせるものがいい。
吉田さんが最初にあげてきてくれたプロローグ原稿は、バンクーバーでのシーンだった。はじめてのオリンピック。ずっと目指してきた夢舞台。20年間のハイライトシーンとして申し分ない。アスリートとしての物語というコンセプトをかんがみても、オリンピックはふさわしいシーンだ。
ところが、本編の原稿が進むにつれて、このプロローグ原稿に、違和感を覚えるようになった。一度目の書き直しをしてもらうとき、吉田さんとこれについても話題にした(後述しますが、本書は全文を二回にわたって書き直しています)。
「プロローグなんですが、これ、このシーンじゃないほうがいい気がします」
「やっぱりそう思いますか。実はわたしもそう思い始めていました。つまり、あのオリンピックは一つの到達点ではあったけど、真央さんのアスリートとしての終着点ではない。だから、あのシーンは、物語のプロローグとしては、ふさわしくないかもしれない」
「確かにおっしゃる通りなんです。かといって、何が正解かということは、
いまは具体的に提案できない状態です。違和感だけ。この原稿は正解ではないという感触だけしかありません」
「なるほど。では、まずは本編をしっかり固めていきましょうか。本編の輪郭がもっとはっきり見えてくれば、自然とプロローグの姿は見えてくるはずですから」
さて、その本編の原稿だが、非常に難航した。筆の早い吉田さんが大苦戦をし、ようやく、真央さんとマネージャーのWさんに見せられるところまで仕上がったのは、全日本選手権を控えた12月に入ったころだった。この時点でも、まだプロローグは仕上がっていない。
全日本選手権で最後の取材を終え、その分の原稿が完成したあともまだプロローグは仕上がっていなかった。
校了日が迫る。しかし、吉田さんもわたしもまだ答えが見えてなかった。
「全日本でしょうかね。吉田さんに水を向ける」
「う~ん、全日本ですか。全日本、全日本…。ドラマチックな試合でした。しかし、今回の物語のプロローグとしてふさわしいかどうか。とはいえ、悩んでいてもしょうがない。それで一回書いてみましょう。わたしも実際書いてみて、書きながら考えてみたいです」
その翌々日に原稿が来た。一読して、結論が出た。
「吉田さん、すみません。これも答えではない」
「ですね。わたしも書きながら、これは違うと思った」
「参りましたね」
「参りました」
「発想を変えてみましょう。もっと短くしてみるとか。よく海外の本にあるような箴言的なものを冒頭に入れるような発想ですね」
「その方向ですかね。わかりました。考えてみましょう」
そこからさらに数日。吉田さんから原稿が来た。
なるほど。そこには、真央さんが中京大のアイスアリーナでウォーミングアップをする様子が描かれていた。どこか特定のシーンを持って来るのではなく、真央さんの、これまでも、いまも、そしてこれからもずっと続く姿、つまり練習のシーンを描く。
今回の物語は、「浅田真央」というアスリートの20年間をたどる物語である。その物語を象徴するオープニングは、これまでのどんな大会のシーンよりも、毎日の練習の風景が似つかわしい。どんなときも、ひたむきに、まっすぐ前に進もうとする強い意志。その姿を描くのが一番ふさわしい。
「さすがだ」
600文字ほどの原稿を見て、ようやく終着点にたどり着いたと思った。しかし、まだ違和感が残る。何だろうか。
「吉田さん、1日だけ時間をください。この違和感の理由を考えて、また連絡をします」
わたしは600文字の原稿を何度も読み返した。声に出しながら。歩きながら。何度も何度も。ああ、そういうことか。見えた気がした。吉田さんに電話をかける。
「吉田さん、もっと短くしましょう。何かが足りないのではなく、多すぎるのかもしれない。さらに短くしてみましょう」
そこから、さらに2日。600文字の原稿は、たった6行になってやってきた。
たった6行だが、その描写には、氷上を一心に滑る真央さんの姿が見える。静かな、しかし、熱い思いも伝わってくる。最初の4行は、一文ごとに短くなることで、徐々に読み手にせきたてるような緊張感を与えていく。そして、最後の2行であざやかに、読者を物語の中にいざなう。
わたしは受話器を取り、電話口に向かって、ゆっくりと力強く言った。
「吉田さん、ありがとうございます。これで、行きましょう」
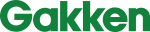


















 ページトップへ
ページトップへ