第1回 「どうしよう。道尾さんはオモシロの人じゃなかった」と思いましたね(笑)(峰)
道尾秀介(作家)対談 「Jam Session」


道尾:『鏡の花』を読んでくださったんですよね。お忙しいのに申し訳ないです。
峰:私、本当は道尾さんの書いた小説を読みたくなかったんですよ。
道尾:え…なんでですか(笑)。
峰:なぜかというとですね、道尾さんとはよくお会いして、私の『アラサーちゃん』がらみのイベントなんかにも来てくださるんですよ。
道尾:自慢じゃないですけど、僕は『アラサーちゃん』のイベントではいつも整理券番号1番なんです。この間も、列の先頭に並んでたんですよね、最前列の席を取るために(笑)。
峰:だから最初の頃は「お知り合いになったし、道尾さんの小説も読んでみようかな」と思ってたんですけど、だんだんお会いしていくうちに、道尾さんは私の中で完全に「単なるおもしろい人」になってしまったんですよ。私の中の道尾像が壊れてしまうと思って、それで読むのが嫌だったんですよね。読んで「どうしよう。道尾さんはオモシロの人じゃなかった」と思いましたね(笑)。

道尾:当たり前じゃないですか。
峰:ねえ。で、すごく単純に感想を言うと、やっぱオモシロからの落差として、「道尾さん、植物のこととかいろいろ知ってて、えらいじゃん!」みたいな気持ちで読みました(笑)。
――『鏡の花』は六つの物語が入った連作集というか、表現は難しいのですが六章で一つの話になるちょっと変わった構成の長篇小説です。
峰:私、群像劇ってもともとすごい好きだし。おもしろかったですよ。
道尾:ありがとうございます。
峰:でも、これってミステリーなんですか?
道尾:僕もジャンル分けはよく判らないんですけど、ミステリーが好きな人が読めばミステリーですし、ミステリーが好きじゃない人が読めばそうじゃないですよね、きっと。
峰:そうなんですね。私ミステリーを読んでも、いつ謎が解かれたのかよく分からないまま読み終わってしまうので。ネタバレとか、誰が犯人なのか、とか最初に言われても全く気にしないし。ミステリーの読み方を全く判ってないので、ミステリーとしてのおもしろさを問われたらどうしようとドキドキしてたんですけど、それは考えなくていいんですね。
――印象に残ったのは六章のうちどれですか?
峰:二章かな。人間があっさりどんどん死んでいくのが好きなんですよ。二章は、通常の死を扱ったものとはちょっと違ってますよね。「病気になって余命何年」、それでみんなが悲しむ、みたいな真っ当な死じゃなくて、人がくだらないことで死んじゃうパターンというのが割と好きなんです。そういう書き方が私にとって、「人が死ぬ」というのを身近に感じられるんですね。人間ってこうやってあっけなく死ぬんだろうな、という予感が昔からずっとあります。だから二章は、「私もこうやって人殺す殺すー」って思って読みました。
道尾:創作の中では、ということですよね。たしかにこの二章のような死の方がリアルなんですよね。不治の病に冒されていて余命がどのぐらいで、というようなシチュエーションの方がむしろありえない。
峰:そうなんですよね。ああいうので人が死ぬのとかは全然好きじゃないです。
道尾:死自体を劇的に描くことを目的にしているものって結構あります。死を劇的にすることで、その周辺の人生をドラマとして書くという。そういうのは僕もあんまり好きじゃないんですよね。
峰:『鏡の花』も死がメインじゃないですよね。死んだあとの「周りの人の生活」というの現実的にはメインになるから。本当はそっちの方がおもしろいなと思っています。
道尾:僕は久世光彦さんの小説がすごく好きなんです。映像作家としても素晴らしい業績を残した方ですけど、何かのエッセイに書いておられたのが、あれだけたくさんのシーンを撮ってきたのに、人が死んだ瞬間だけは一度も撮ったことがないそうなんですね。波瀾万丈な人生を送ってこられた方なので、人の死の悲しさとか、周りにいる人の気持ちとかは、判りすぎるくらい判っている。それを劇的に撮ることなんて自分にはできない、と言っているんですよ。
僕にもそういう気持ちはあります。死をことさらに劇的にする必要はなくて、淡々と書くだけでも読者は感じてくれる。だからそんなに克明に書く必要はないと思っています。

峰:そもそもなんで、いろいろな人がどんどん死んでいく話を書こうと思ったんですか?
道尾:全てが明るい世界ってないんですよね。光があるところには絶対どこかに影が落ちるという事実を書きたかったんです。六章をすべて読み通した時にそれが分かるような構造にしたかったんですね。と同時に、それぞれが短編として成立していることも大事でした。
峰:読んで思ったのが、キャラがけっこうたくさん出てくるのに、それぞれについての詳しい「こういう外見で」とかそういう描写は全然ない。でもすごく想像がつくというか。
道尾:それは一番ありがたいですね。
峰:この人は学校の中でどれぐらいのポジションなのか、とかそういうのがよく判ります。
道尾:いわゆるスクールカーストですよね。峰さんがよく言われている。
峰:第五章だったかな。お姉ちゃんと弟が二組出てくる話があるじゃないですか。で、自転車を捨てた弟のお姉ちゃんの方。真絵美ちゃんか。あの子はちょっとブサイクなんだろうな、と思うんですよ(笑)。
道尾:学園ドラマでいうと、ピントが合ってないところに映っているような感じの子なんですよね。実際の暮らしの中でも「どういう人か憶えているし、どんな話をしたか憶えているけど、名前がどうしても思い出せない人」っているじゃないですか。でも、その逆って実はあまりないんですよね。「名前は憶えているけどどんな人だっけ?」というのはまずない。だから、本当にそういっていただけるとありがたいですね。血肉を伴った人間が書けたな、という気がします。 僕は趣味でシャンパン・キャップ・マンを作ってるんですよ。シャンパン・キャップにワイヤーで手足をつけて、帽子をかぶせたりして人形を作るんですけど。ある時、マッシュルーム状のシャンパン・キャップで、人形だったらちょうど顔にあたる位置に会社のロゴが刻印されていて、それが上弦の月のような状態で入っているのがあったんです。まるで口みたいで。「これはシャンパン・キャップ・マンのためにできたようなコルクだ」と思って、人形を作ったんですね。そうしたら、案の定笑った顔になったんですけど、飾ってみたら、シャンパン・キャップ・マンの中で、そいつだけむしろ表情がないんですよ。口があるのに、並べて見た時にそいつだけ表情がないんです。他のやつはこっちの気分によっていろんな見え方をするんですね。具体的な容姿というのは、描きすぎるとかえって人間らしさから遠ざかってしまう。
峰:人形がめっちゃ好きなんですね(笑)。キティちゃんに口がないのもたしかそういう理由なんですよね。いろんな表情に見えるようにという。
もくじ
僕の書くようなものって、物語が先にあって、それが鋳型になってキャラクターができるような感じなんですよね。(道尾)
道尾:実際人に会っても、これは女性は違うのかもしれませんが、相手がどんな髪型をしてたとかどんな服を着ていたとかは、家に帰っても思い出せないですね。でも、話したこととかちょっとした仕草とか香りとかはよく憶えている。だから外見に関しては、「描写してもあまり意味がない」という気持ちがあるんです。

峰:確かに。私、小説でやたら登場人物全員に服装の描写とか入ってくるのが好きじゃなくて。服にすごく詳しい人とか、着物の柄とかならキャラが見えてくるからいいんですけど、特にファッションに詳しくないおっさんが書いてる服装の描写って……なんか「ベージュのニットに青いスカート」とか書かれても全然分からないんです。ページのムダだから全部カットしろよってよく思ってるんですよ。
道尾:その話になるといつも思い出すのが、また久世光彦さんなんですけど、あの人の小説の中に、少年が年上の女性に憧れるシーンがあるんです。でも、その女性について、どんな容姿かはまったく書いてないんですね。そのかわり、たったひと言「紫の帯がよく似合う人だった」と書いてある。それだけでもう、読者の頭の中では完全に人間ができあがってしまうでしょう。大人っぽい妖艶な感じのスッとした女性。すごいテクニックだなと思いました。そこまでの力は僕にはまだないですけど、そういうことをやりたいんです。
――キャラクターをどう書くかとかキャラクターをどう印象付けるかということを作家として道尾さんどうお考えですか?
道尾:僕の書くようなものって、物語が先にあって、それが鋳型になってキャラクターができるような感じなんですよね。でも峰さんの『アラサーちゃん』は、キャラクターが先にあって、彼らが毎回いろんなストーリーを引き起こす。キャラクターと物語の因果関係が逆なんですよ。僕は終わりのあるものを書いているからなんですけど、『アラサーちゃん』は4コママンガだから、たぶんエンディングってないですよね。でもいろいろな人間関係は変わっていく。最近だとサバサバちゃんが急にきれいになってます。そういう変化は見ていて面白いですが、それは起承転結の結に向かっているわけじゃないんですよね。

峰:どうなんですかね。一応、関係性は変えていこうと思ってますけど、それは起承転結が小刻みにあるのを飽きさせないための工夫でしかないので。その流れで物語を作ろうみたいなのはあまりないですね。
道尾:そこが大きな違いだと思います。だからキャラクターと物語の関係が逆になるのかなと思っていて、例えば『鏡の花』の場合、それぞれの章で短編としても読めるので、起承転結が5回あるといえばあるんですよね。その全体がいつの間にか起承転になっていて、通して読むと第六が結になっているという本。僕の本の中でもちょっと難しい構成ですけど、『アラサーちゃん』にもし最終回があったら、これは似たような構造になりそうですよね。「起承転結が繰り返されて、最後に大きな結が来る」という。
峰:ああ。そんな風にいけるのかどうかよく分からないですけど。4コマものの連載が長く続いたやつはだいたい、最後に今まで登場したキャラが出てきて、「これで最終回だよ。みんなありがとう!」みたいな、そんな終わり方じゃないですか? まあ、それでいいかなと思ってるんですけど(笑)。
僕自身、キャラクターものは大好きなんですけど……長く書き続けたくはないんですね。(道尾)
――道尾さんは、キャラクターがあって、そこに物語を作っていくタイプの小説というのはお書きにならないのですか?

道尾:『カササギたちの四季』がそうかなとは思います。必ず華沙々木くんが、できもしないことをできるといって、日暮くんが必死でカバーするという。僕自身、キャラクターものは大好きなんですけど……長く書きつづけたくはないんですね。書き始めた時点で、3人トリオがいたとして、たとえば「その中の誰も死なない」という事実は最初から判ってるじゃないですか。それだけで制約になっちゃいますし、物語の幅が狭められて。その3人が要になることで広がりに限界が出てきてしまうんですよね。だから、読むのは大好きだけど、あまり書かないんです。
峰:ああいうのはすごく向き不向きがあると思っています。人柄が出てくるというか。人柄が悪い作者が書いても、全然おもしろくならないんです。
道尾:ルパン3世とか、最高に面白いですよね。シャーロック・ホームズにも愛着がありますし、金田一耕助とか、キャラクターものは本当に好き。でも、やっぱり読むのと書くのはちがうんですよね。
例えば『アラサーちゃん』でも、描きながら関係性が変わって、フッと気付いていつの間にか誰かと誰かがくっついていたりという「想定していなかった話の変化」があると思うんですけど、小説だと、書きながらそれが常に繰り返されていくんです。あらかじめ大体のストーリーは決めているんですけど、書いていてそれ通りになることはまずない。例えば、セリフの書き方が2パターンあるじゃないですか? まず「確かにそうだね」といったセリフが出てきて、改行せずに「彼は言った。」と続け、そのまま下に台詞の続きを書くというパターンと、「彼は言った。」の前後を改行して、そこだけを独立の行で書くパターンです。あることを登場人物に言わせようとしても、ページをひらいたときに文面の見た目がきれいじゃなかったりすると、台詞を変えたりもする。ということはこれ、文体が人物を変えちゃってるんですよね。違うことをしゃべらせちゃう。そうやって違うことを喋らせると、その違いの積み重ねでストーリーまで変わってくる。それがやっていてすごくおもしろいです。

峰:私は人物の台詞をどういう記号で書くかがいつも気になります。カギカッコの人も多いですけど、ダッシュ(――)で書く人、特に何もつけずにそのまんま改行だけでポンポン書いていく人もいるし。そういうのを見るのが好きですね。
道尾:僕は、過去のセリフはダッシュで書いて、今のセリフはカギかっこで書くという、一応のルール付けをしているんですね。読者が混乱しないように。それと、電話は二重カギかっこです。さっき言った「言葉があって改行なしで地の文。で、またカギかっこ」というのは、実は1回もやったことないです。改行を減らすことで省スペース化できるような気がしますけど、実は、それで原稿の枚数が減るかといったら、全体的にいうとそんなに減らないんですよ。だったら見た目が判りやすい方がいいかなと思ってカギかっこは一番上にしています。
――それが道尾さんにとっての「文体」なんですね。
道尾:そうですね。見た目のビジュアル。紙の、黒い部分と白い部分の比率もその一部だと思っています。
司会・構成:杉江松恋 撮影:干川修 2014年7月11日
作品紹介

鏡の花
製鏡所の娘さんが願う亡き人との再会。少年が抱える切ない空想。姉弟の悲しみを知る月の兎。曼殊沙華が語る夫の過去。少女が見る奇妙なサソリの夢。老夫婦に届いた絵葉書の謎。ほんの小さな行為で、世界は変わってしまったーー。六つの世界が呼応し合い、まぶしく美しい光を放つ。まだ誰も見たことのない群像劇。
プロフィール
峰なゆか

1984年生まれ。漫画家・文筆家。主な著作に「アラサーちゃん無修正」(扶桑社)「恋愛カースト」(宝島社、犬山紙子との共著)など。ドラマ「アラサーちゃん無修正」は毎週金曜深夜0時52分よりテレビ東京系列で放映中!
道尾 秀介
1975年東京都出身。2004年、「背の眼」でホラーサスペンス大賞特別賞を受賞し、作家としてデビュー。2007年「シャドウ」で本格ミステリ大賞、2009年「カラスの親指」で日本推理作家協会賞、2010年「龍神の雨」で大藪春彦賞、「光媒の花」で山本周五郎賞を受賞。2011年「月と蟹」で直木賞を受賞。近著に「カササギたちの四季」「水の柩」「光」「ノエル」「笑うハーレキン」などがある。
バックナンバー
- 第2回 私、いまだになんで道尾さんが『アラサーちゃん』がこんなに好きなのか把握できてないんですよね。(峰)
- 第3回 よく考えてみるとアラサーちゃんのキャラって、判りづらいんですよね。そこがドラマでは判りやすい感じになっていると思いました。(峰)
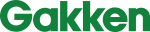

















 ページトップへ
ページトップへ