
「本屋さんのココ」、第4回のテーマは「本屋さんと選書」。東京都文京区白山にある「双子のライオン堂」に伺いました。
双子のライオン堂は2013年に店主の竹田信弥さんが始めた、新しい本屋さん。その特徴は「選書」専門店であること。店には辻原登、山城むつみ、東浩紀、など、著名な批評家、小説家の選書した本が並びます。
(双子のライオン堂、選書者の一部→ http://liondo.jp/?page_id=23)
なぜ「選書」専門店のスタイルが生まれたんでしょうか。また、本屋さんが減っている、と言われるなかでどうして、そしてどうやって双子のライオン堂をオープンしたんでしょうか。しかも最近、双子のライオン堂で「本屋入門」という本屋さんのための講座も行っているようなのです。これは話を聞きに行かないと!
今回は、講座「本屋入門」の共同企画者でもあり、本屋をもっと楽しむポータルサイト「BOOKSHOP LOVER」を運営していて、竹田さんとも親交の深い和氣正幸さんをお呼びし、一緒にお話を伺ってきました。
「本屋さんのココ」では私と一緒に毎回色々な人に実際に“本屋さん”を楽しんでもらいながら読者の視点にたったレポートも加えてお伝えしていこうと思います。
取材日:2015年2月28日
取材:和氣正幸、松井祐輔
構成、写真:松井祐輔
【店舗情報】
双子のライオン堂
〒113-0001
東京都文京区白山1-3-6
営業日:毎週火曜日、土曜日 13:00〜21:00
和氣:店の本棚も、自分たちで作っていったんだよね。
竹田:小さな本棚は間伐材を買ってきて、自分でつくりましたね。
松井:この大きな本棚はどうしたんですか。

竹田:これはIKEAで買ってきました。1本1万円もしなかったと思います。他には自宅から持って来たりして、ほとんどお金をかけていないですね。店内も自分たちでペンキを塗りましたし、照明の取り付けなんかもやりました。唯一こだわったのは入口の扉ですね。もともと倉庫だったので、入口はシャッターだったんです。でもさすがにそれは味気ないので。そこでフランツ・カフカの生家を意識して、扉と外壁のデザインをしてもらいました。他はほとんどお金をかけていないのに、ここだけは20万円くらいかけちゃいましたね(笑)。

●フランツ・カフカの生家の写真

●「双子のライオン堂」正面
松井:すごい。そっくりですね!
竹田:チェコ旅行帰りの人が、たまたま通りかかって店に入ってきたことがありましたね。「さっきまでチェコでこの場所にいたんですけど!」って。
和氣:それはすごいなぁ。
松井:窓枠まで再現したんですね。
竹田:そこはこだわっちゃって。でも木の扉は町中を探してもらってきたものなんですよ。だから20万で済んでいるんです。いまって、木の扉なんてほとんどないじゃないですか。雨ざらしになるものだから、ちゃんと加工してあるものじゃないと使えないし。そこで町中を回って、解体中の家に声をかけたんです。いくつか断られましたけど、何軒目かで、結果的にもらってくることができました。

【100年続けるために−−週休5日の本屋】
松井:店の営業は火曜日と土曜日の週2回ですよね。
竹田:それ以外は他の仕事をしています。店にもほとんどその日しかいないので、本の入れ替えも営業しながら、お客さんにも手伝ってもらいながらやっちゃいますね。
和氣:そういう形態で続けて、もう2年だよね。営業日は増やしていかないの?

竹田:いろんな人に「毎日やればいいのに」とは言われるんです。でも、そうやって毎日やることで、どこかにしわ寄せが来ると思うんですよ。ライオン堂は僕がやりたくて始めた店で、そこに来てくれるお客さんがいる。それで僕が疲れたからやめる、というのはかなり無責任なことだと思っていて。コミュニティっていろんな人が関わっているので、その母体となる店が個人の都合で辞めてしまうのは無責任だと思うんです。もちろん、やむを得ない事情もあると思うんですが、辞めないこともひとつの勇気、挑戦だと思って。
高校生のころから10年間ネットで古本屋を続けて、続けることで何かが起こる、というのは身をもって体験しているんですよ。それこそ、規模は小さくても辞めずにやり続けたことで、いまのライオン堂に繋がっているわけで。理想としては100年続けたい、という気持ちがあるんです。ビジネスで考えると、100年続けるためには絶対に2代目が必要じゃないですか。そういう意味で「一生」ということを目指しているんです。だから無理はせずにできる範囲で最大限にやる。それをお客さんに理解してもうために、本屋として営業している間は、とにかく精一杯やる。
松井:100年続けるための週休5日でもあるわけですね。
竹田:それって、僕には全く違和感のないやり方だったんですよ。利益体質というか、利益を求めるあまり、やっている側に負担がかかりすぎることがあると思うんです。そういうのを見ていると、「店のほうにもいいペースがあるんじゃないかな」と思って。
松井:「店のほうのいいペース」。
竹田:驕りかもしれないけれど、店がお客さんと立場、目線を一緒にすることが大事だと思うんです。これからのビジネスとして、そういう考えはあり得るかもしれないと思っていて、特に本屋はそれが出来やすい仕事なんですよ。さすがに毎日食べるもの、例えば八百屋さんが不定期営業だと、困るじゃないですか。でも本屋って毎日なくてもいいものなんですよ。だからお客さんが本を買いたくなるタイミングと営業のサイクルが合っていれば、別に毎日やらなくてもいいと思うんです。
和氣:立地的にも平日昼間の営業は難しそうだよね。
松井:逆に言うと、そういう場所なら家賃も安いですよね。
竹田:ライオン堂みたいに町外れで、駅からも遠いし通勤ルートでもない場所にある店だと、お客さんや気が合う仲間たちのサイクルに合わせながら、柔軟に営業形態を変えていってもいいのかな、と。毎日開けても店の売り上げだけじゃ僕の生活が成り立たない、ということも確かにあるんだけど(笑)。
【消費しない本の「読み」方とライオン堂のこれから】
松井:そういうお客さんと合わせる形で、イベントが増えていったり、店も変わっていくんですね。
和氣:最近は、もっと本を「読んで」ほしいという話もしていたよね。
竹田:そうなんですよね。いままでは「売ること」をしていたんですけど、「読むこと」にもっと目を向けていきたいな、と。お客さん、特に若い大学生や社会人の人と話をすると、「たくさん本を読むんだけど、しっかり読み込めないんです」という悩みを聞くんですよ。ライオン堂でも読書会をやっているし、本を読んで誰かと語り合いたいという気持ちもあるんですが、逆に自分の中だけで反芻するような時間、そういうものがどんどんなくなっちゃっている気がしていて。そういう時間を取り戻したいんです。昔の文学者って、読後にしょっちゅう散歩しているんですよ(笑)。でもそうやって感覚が広がると、本の“読み”も広がる、というか。いまは「この本を読んだら次、その次はこの本」って、どんどん消費しちゃっている気がして。次の本を紹介したりすることは、本屋としては正しいんだけど、読み手のことを考えたらいいことばかりじゃないような気がして。具体的に何ができるかはまだわからないんですが、ライオン堂では「読む」という行為も考えていきたいと思うんです。
和氣:竹田くん自身、小説を書くことを意識していた時代があるよね。そういうことといまの考えって繋がっているの?
竹田:ちゃんと「読め」れば、「書く」こともできるとは思います。そういうなかで将来ライオン堂のお客さんから作家が出てくれば嬉しいですね。それこそフランスのシェイクスピア・アンド・カンパニー書店みたいに。それはひとつの夢かも知れないですね。
和氣:ライオン堂が創作のプラットフォームになってほしい、ということなのかな。
竹田:そこまでは考えていないですけど、「読む」ことと「書く」ことは表裏一体だと思うので、その手助けができればと思います。

松井 祐輔 (まつい ゆうすけ)
1984年生まれ。 愛知県春日井市出身。大学卒業後、本の卸売り会社である、出版取次会社に就職。2013年退職。2014年3月、ファンから参加者になるための、「人」と「本屋」のインタビュー誌『HAB』を創刊。同年4月、本屋「小屋BOOKS」を東京都虎ノ門にあるコミュニティスペース「リトルトーキョー」内にオープン。
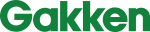

















 ページトップへ
ページトップへ