戦後を生きる子どもたちの教育と未来のために奮闘した編集者たち──。『学研の科学』誕生秘話
『学研の科学』復刊!『大人の科学マガジン』統括編集長・学研科学創造研究所所長 西村俊之インタビュー

2022年6月、学研のふろく付き学習誌『1~6年の科学(以下、『科学』)』が『学研の科学』として復刊する。1963年に創刊され、姉妹誌『1~6年の学習(以下、『学習』)』とともに最盛期には670万部という驚異的な発行部数を記録した伝説的な媒体だ。しかし“国民的学習誌”と言われるまでの道のりは、常に降りかかる難題との戦いの連続だった。
今回、その歴史を語ってくれたのは、学研科学創造研究所所長、西村俊之。『科学』の編集長を歴任、現在は『大人の科学マガジン』統括編集長もつとめる。入社以来30年以上、学研の科学とともに歩んできた。
創刊から60年近い年月を隔て、『科学』誕生の秘話が、当時の貴重な資料とともに、西村の口から蘇る。
もくじ
戦後復興への願いから生まれた、学研と『学習』

太平洋戦争終結後の小学生が使っていた教科書は、多くの箇所が戦中からの教科書の各部を墨で塗りつぶしたものだった。これは“敗戦”と同時に進駐してきた、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の指示によるもの。つまり、当時の小学生は、満足に勉強ができる学習用教材を持っていなかったのだ。
この状況を憂い「戦後の復興は教育をおいてほかにない」と古岡秀人が立ち上げたのが、学習研究社(学研)という会社であり、教育誌『学習』であった。
「1947年に『初等五年の学習』『初等六年の学習』として創刊した『学習』は、順調に部数を増やしていました。一方、そのあとに作られた『科学』がスタートしたきっかけは、1954年に施行された理科教育振興法でした。これからの日本は、科学技術立国を目指すんだという指針ですね。この法律をうけて文部省でも、小学校教育において理科が重要だ、となるわけです。そこで学研でも『学習』のほかに、理科や算数を中心とした科学誌を作ろうとなったのがはじまりでした」
伸び悩む部数。その危機を救ったのは“駄菓子屋の虫眼鏡”

学年別月刊雑誌として創刊した『学習』とは異なり、『科学』は、当初学年別ではなく『小学生のたのしい科学』という雑誌を出版するところからはじまった。
「当初は書籍の部門が作ったものだったこともあって、なんとなく図鑑っぽいというか、雑誌というよりも書籍然としたつくりでした。販路を変えたり、誌名を変えたりと手を尽くしましたが、科学史はなかなか部数が伸びませんでした。こうしたなかで『学習』編集部に在籍していた中川浩さんが、テコ入れのために科学編集部にやってきました」
中川は、もともと高校の物理の教師だったが、教育に対しての考えが当時の校風とあわず、学研へ転職したという異色の経歴を持つ編集者だった。
テコ入れをまかされた中川だったが『科学』の部数はいっこうに伸びず、悩みを深くしていた。そんなある日、中川は自分の子どもたちが庭で遊んでいるのを眺めて、ある発見をする。
「子どもたちが何かを持って遊んでいたそうです。それで子どもに『それはなんだ?』と聞くと、駄菓子屋で売っている“虫眼鏡“だというんです。
それを手にした中川さんは、一見おもちゃにも見える、駄菓子屋の虫眼鏡でも、太陽光を集めるなど方向性を示せば、十分に科学的な実験ができることに気づいたそうです。そうか、こういう体験を、僕らは子どもたちに伝えなきゃいけないんだよな、と。思い至ったというか、気づいたわけですね」
中川はその後、駄菓子屋をはじめ、様々な場所に赴き、調査を始める。どんなものが置いてあるのか、いくらで売っているか、流通がどうなっているのかなどを、ひとりで調べ歩いた。
すべては、科学実験に通じるアイテムを付録にした本を作るためだった。『○年の科学』創刊の曙光だった。
“玩具をつくるために入社したんじゃない”編集部の反発と説得

中川が、まずやらなければならなかったのは、編集部員を説得することだった。
当時の編集部員は、中川が来る前から理科や算数系の本を作ってきた自負がある。「どうして、他部署から来た人に、あれこれ言われなきゃいけないんだ」という反発もあった。
「それでも中川さんは、独自で調べあげた情報などを持っていき『こういうものを付録にした本を作ろうと思うんだけど、どうだろう?』と部員たちに提案した。はじめは、『いやいや、僕たちは本を作るためにこの会社に入ったんです。玩具を作るために入ったんじゃありません』と強く反発されたそうです」
しかし中川は、粘り強く部員たちに語りかけ続けた。科学のおもしろさを、子どもたちの元へ届けたいという中川の情熱は、次第に編集部員たちの心を動かしていった。『科学』創刊に向けて、編集部の士気は上がっていった。
無理難題からの奇跡の大逆転。ひと晩で書き上げた、144の企画書

しかし説得せねばならないのは編集部員だけではなかった。中川の考える付録付き『科学』創刊のためには、付録の調達とコスト、顧客へ届けるための流通の問題など、数多くの課題がある。これらを解決し、役員を説得する必要があった。
何度もダメ出しをされながらも、粘り強く説得を続けていた中川。そんななか絶体絶命の日が訪れる。渋りつづける役員が、無謀とも思える条件を突きつけてきたのだ。「翌朝までに6学年・3年分の企画を立てろ」と。つまりひと晩で、およそ216もの付録付きの企画を用意することが、創刊の条件となった。
中川は編集部に戻り、
「科学雑誌に携わる、多くの編集者が夢見てもできなかったことを、『科学』で実現してみないか。なんとか、朝までに、3年分のプランを作ってほしい」
と部員に伝えたが、無謀とも言える課題に、皆黙ったままだったという。すでに、夜の11時を過ぎていた。
さすがの中川もその様子を察し、諦めた様子で部を後にした。
しかし、残った部員は、中川の真意について皆で話し合い、そして、心を決める。
「中川さんは、たったひとりでここまで動いてくれた。子どもたちに科学を伝えたい気持ちは、俺たちも一緒だ」
こうして編集部員は、心をひとつにした。
すでに、文部省の学習指導要領を熟知していた編集部員たちは、小学1年生が理科で勉強する1年間の流れを理解していた。これを元にして、『科学』に必要な1年分の付録アイデアを次々とだしていった。
「そして翌朝。出社してきた中川に『3年分は無理でしたが、2年分までは用意できました』と、6学年2年分、144の企画が手渡されたそうです。役員も本当に無理な要求をしたものです。しかし、この2年分の企画書を見せられた役員は、その熱意を前に、さすがにNOとはいえませんでした」
やがてこの企画書は、役員だけでなく、会社組織全体を動かしていく――。
「今考えても信じられないのですが、この時、6学年分なので6つの編集部が、同時期に動き始めたんですよね。
しかも彼らは、4月号を作りながら、7月号の付録づくりを同時進行で進めるというような、超過密スケジュールで動き続けていたんです。
会社全体が一致協力しないと実現できないことであり、これはもう奇跡と呼んでいいんじゃないかと思います」
一夜で編集部員たちが生み出した付録のアイデアとパッションが、『科学』の土台になったのだ。
ノーベル賞科学者・湯川秀樹に車中で直談判

編集部員と中川の“子どもたちのためになるものを作りたい”という強い思いで生まれた『科学』には、数々の伝説的なエピソードもある。
中川がやって来る前の混迷した科学編集部が事態を打開するために熱い視線を送っていたのが、日本人として初めてノーベル賞を受賞した物理学者の湯川秀樹氏だった。当時、何度目かの再創刊だった科学誌の監修を依頼すべく、多忙な湯川のスケジュールの合間を縫い、特急電車に同乗し、車中の通路で湯川に頭を下げた。
「ノーベル物理学賞を受賞した後で、先生が多忙を極めていた時期でした。学会で来ていた東京から、京都へ帰る移動の間なら、話を聞く時間がある、と言われたそうです。そこで編集部員が、まだ新幹線が開通する前の、東海道本線の特急こだまに乗ったわけです。湯川先生に雑誌の趣旨を説明して、ぜひ監修をお願いしたいと頼み込んだのです。
先生は『その雑誌は売れているんですか?』と尋ねたそうです。編集部員は『まったく売れていません』と正直に答えました。すると、驚いたことに、湯川先生は『それじゃあ、監修を受けましょう』と応じてくれたのだそうです」
その後創刊された学年誌の『科学』でも、湯川秀樹を筆頭に、東京大学の学長や国立科学博物館の館長など、そうそうたる人物が監修者として名を連ねている。これは当時の日本の多くの賢人たちが、子どもたちの教育に対して、なみなみならぬ思いを抱いていたことの証だろう。
創刊早々の部数低迷、編集部の反発、会社からの無理難題、物流の問題…。『科学』が誕生・成長した裏には、諦めそうになる心を奮い立たせて戦った、歴代の編集者たちの苦労があった。
編集部の本気が表れた本格付録

西村は、今も編集部に残る、当時の付録のいくつかを見せてくれた。
「『虫集めセット』とか、すごいですよ。ちょうちょのはねを伸ばす展翅板があって、ピンもありますね。説明には当たり前のように『ここにナフタリンを入れましょう』とか書いてある。今だと、子ども向けには売れないですよね(笑)。もう、驚くほど本格的な昆虫採集セットなんですよ。図鑑でみるような、どこで手に入るんだろうと思っていた本格的な器具、それが、ふろくなんです。
極めつけは、この1965年の臨時増刊号の『解剖セット』です。まな板のようなものがあって、メスや注射器が付いています。“本気の実験教材”だったんです。
創刊した1960年代の当時は、学校で理科の実験をやるにも、実験道具が一人に1つではなかった。それを一人ひとりに届けたいという思いも強かったようです。本当にすごいですよ」
そうした熱意が子どもや親たちに届いたのか、『科学』は、創刊から順調に読者を増やしていく。例えば、創刊6年目にあたる1969年の『1年の科学』9月号では、実売が約60万部。1年から6年までだと、約300万部、『学習』も合わせると約600万部となる。最大部数を記録しているのは、1979年だが、創刊から時を経ずに、国民的教育誌へと成長を遂げていたのだ。
「体験」より「結果」が重視される時代に

当時の付録と、後年の付録を比較すると「だんだんと子どもに優しくなっていった」と、西村は言う。受験戦争に象徴されるような“成功”や“結果”重視の時代の流れ、“できない”や“失敗”から得る価値を認めない社会風潮が、“体験”をテーマとしてきた『科学』の付録にも、影を落とし始めていた。
「例えば鉱石ラジオは人気で、何度も付録化されています。部品の中に、円筒に銅線を巻いたコイルがあるんですよね。この銅線ですが、当初は子どもたちが自分で巻くようになっていました。でも、時代を経ていくうちに、だんだんと銅線を上手に巻けない子どもたちが増えていきました。上手くコイルが巻けないと、ラジオが聴けないんです。だから、付録では最初から銅線の巻いてあるコイルを付けていくようになるんです」
本当は、子どもたちに銅線を巻いて欲しいという。だが、子どもにとってはコイルも巻けず、ラジオも聴けなかったとなると、苦い思い出だけが残ることになる。編集部としては、苦渋の選択で、あらかじめ銅線を巻いたコイルを付けるようになったのだという。
子どもたちには、ぜひ“失敗”も経験してほしい
 西村自身も、子どもの頃に『科学』の読者だったひとりだ。しかしその付録では、失敗の記憶の方が強く残っているという。
西村自身も、子どもの頃に『科学』の読者だったひとりだ。しかしその付録では、失敗の記憶の方が強く残っているという。
「例えば棒温度計が付録の号。学校で、理科の時間にだけ使える棒温度計と同じものですね。『すごい! 理科の時間に使ったのと同じやつが届いた!』ってうれしかったのを覚えています。うれしくて、いろんなものの温度を測っていたら、赤いアルコールが、途中でプツンッて切れてることに気付いたんです。どうすればいいかを考えて、この赤いのを一番上まで上げれば、直るんじゃないかって考えて、ガスコンロの火の上、高いところにかざしました。『おお! 上がって来たあ~!』と思ってたら、1番上まで上がったところで、液溜めが、パリンッて割れちゃって(笑)。今日届いたばかりなのに…やばい…と思ったことは、よく覚えています」
また、アリの飼育キットでも失敗したそうだ。
「アリをいっぱい集めたくて、あちこちの巣から集めました。翌朝、巣ができていることを期待しながら見たら、なんと全滅。中でアリ同士がケンカしたみたいなんです。学研に入社してから、アリの飼育キットの説明をよく読んだら『ひとつの巣から取ってきてください』って、ちゃんと書いてあるんですよ(笑)。
こういう失敗は、子ども心にはたしかに失敗だったのだけれど、それがこんなに記憶に残っているってことは、ある意味で大成功だったんだなと思うんです。
子どもたちは、これから先、失敗することだらけだと思います。その時に、過去の失敗体験というのは、大きな“財産”。成功するためにも絶対に大事なものなんですね。失敗から新しいアイデアのヒントを得たり、気持ちを前向きにどう立て直したりするかとかね。だから、ぜひいろんな失敗をしておいて欲しいという思いがあります」
経験よりも“知っている”ことが偉い時代にこそ「失敗の経験」を

だが、現代はどうだろう。スマホを見ればすぐに正解の情報にたどり着く便利な現代では、子どもたちが失敗できる機会は少なくなっている。そして“世の中は知らないことであふれている”ということ自体に気づく機会も減っていると、西村は感じる。
「情報があふれすぎているんですよね。例えば、シャーペンの芯に電気を流して電球を光らせるという科学実験を、子どもたちの目の前で実演すると、子どもたちが口にする言葉は『あぁ、それ知ってる!』なんです。でも、実物は見たことはないでしょ? と聞くと『YouTubeで見た!』って。
Webや動画サイトによって『知る』ことは大切です。しかし、与えられた情報を『知っている』だけで世界のすべてを『知っている』気になってしまうことには、僕は危機感を感じます。世界にはまだまだ『知らない』ことがある、世界は思ってもみなかった可能性にあふれている。そのことを『知る』ために、子どもたちにはみずから手を動かして、実験して、体験してほしい、失敗も含めて。そう思っています」
一方で、子どもたちが科学に無関心になっていることは決してない、とも西村は言う。YouTubeの科学系チャンネルでの実験動画は、多くの視聴回数であることからもうかがえるし、かつて学研が行っていたアンケートでも、“理科“は必ず好きな教科の上位に入っていた。
新時代の『科学』が導く、子どもの未来

『学研の科学』の復刊にあたって、現在の西村はアドバイザーという立場だ。
「僕たちがあれこれ言い過ぎないほうが、新しい時代の『科学』ができて、想像もしなかったような面白いものになっていくと思うんです。僕たちが考えつくようなアイデアを、復刊で実現してほしいとは思いません。“復刻”ではなく“復刊”なんだから、今の時代のひとたちでしか作れないものを作ってほしいですね」
西村は『科学』の未来に、なにを見ているのだろうか。
「まずは、かつての『科学』を作ってきた僕たちをびっくりさせるもの、感動させるものを作ってもらいたいですね。大人が感動しないようなものでは、子どもも感動しない。
そういうものができれば、受けとった子どもたちも必ず“わあっ!”って驚いてくれる。すべての学びのはじまりは“驚き”だと思うんです。やってみて、驚いて、失敗して。なんでだろう、って考えて。そして、またやってみて、失敗して…。大人はとかく、やりかたを教えて、答えに導くお膳立てをしがちですけど、それだと答えが出たらそこで終わりなんです。そうじゃなくて、驚いて不思議に思うきっかけと、環境を与えられたら、それで大成功だと、僕は思っています。
子どもたちが、自分が感じたこと、やったことを、失敗を含めてどんどん増やしていけるようなものになっていってくれたら『学研の科学』の復刊は大成功だと思っています」
子どもたちの未来を祈り創刊された学研の『科学』は、誕生から半世紀以上の時を経て、令和の時代に復刊となる。
いまの時代を生きる子どもたちが忘れかけた驚きと“トライ&エラー”の体験を届けるため、新たな奮闘は始まったばかりだ。
(取材・文=河原塚 英信 撮影=多田 悟 編集=櫻井 奈緒子)
クリエーター・プロフィール
 西村俊之(にしむら・としゆき)
西村俊之(にしむら・としゆき)
福岡県出身。早稲田大学第一文学部を卒業後、1989年に学習研究社(現・学研ホールディングス)に入社。『学習』『科学』編集長を歴任後、現在『大人の科学マガジン』統括編集長、学研科学創造研究所所長。
あわせて読みたい
-

あの『学研の科学』が復刊! 創刊号のキットは“未来のクリーンエネルギー”水素をつくり燃料にして飛ばすロケット!
こどもの本
-

2022年『学研の科学』が復刊! 世界を作っていく子どもたちに贈る、科学がつなぐ未来とは──
こどもの本 クリエイター・インサイド
-

計50名様!『学研の科学 大図鑑プロジェクター』先行モニター募集! ~〆11/20(日)
イベント・キャンペーン こどもの本
-

フォロー&いいね!で【本のクリスマスギフト
が30名様に当たる!】プレゼントキャンペーン開催中(~12/3〆)
イベント・キャンペーン こどもの本
-

『学研の科学 ときめく実験鉱物と岩石標本』が大人気!発売5か月で6万部!
こどもの本
-

「クイズで学ぶ科学イベント みんなで選ぶ恐竜ランキング」を12月26日(月)無料開催
イベント・キャンペーン こどもの本
-

計50名様!『学研の科学 ときめく実験鉱物と岩石標本』先行モニター募集! ~〆11/12(日)
イベント・キャンペーン こどもの本
-

『学研の図鑑 LIVE』編集者が疑問に答えるライブ配信を 6 月から 3 か月連続開催!
イベント・キャンペーン
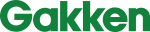

















 ページトップへ
ページトップへ