
口で書いた初めての文字 1972年
びわ 1973年
初めて筆を口にくわえて「ア」という字を書いたのが、入院して二年目の一九七二年のことだ。黒い糸の切れ端がもつれるような、ミミズがのたくったような字だった。目がまわり、よだれを垂らし、吐き気をもようしながら、文字の練習をした。
入院中お見舞いの手紙をたくさんもらい、一行でもいいからお礼の返事を書きたかった。そしてなんとか短い手紙が書けるようになったが、文字をたくさん書くのは大変で、どうしても便箋に大きな余白が残ってしまった。その余白にお見舞いにいただいた花の絵を描いてみた。なんの絵だかわからないような下手な絵だったが、次第に絵を描くのが面白くなった。
いくつも手紙を書いているうちに、絵を先に描いて、そのまわりに手紙を書いた方がバランスよくかけることに気づいた。この、びわの実の絵は、やはり友だちに出そうと書いたものだが、出すのをやめて残ったものだ。
油性の黒のサインペンで輪郭を描いて、水性のカラーサインペンで色づけしていく。サインペンを使ったのは、色をつくらなくてもよいし、口にくわえやすかったからだ。
どのくらいの数の手紙を出したかはわからないが、友だちが大事に保存しておいてくれたものもあって、今見ると下手な文字と絵だが、懐かしさが込みあげてくる。
〝詩画〟というスタイルが芽生えたのは、このころだ。

菊の花 けがをしてちょうど三年目 1973年
お見舞いの花キリン 1973年
柿、菊、ミョウガ。なんとか絵を描く。 1973年
けがをした日からちょうど三年、一九七三年六月十七日に描いた絵。六月に菊というのも不思議だが、大学病院の売店には、透明なラップにつつんだ、お見舞い用の菊の花束がよく並んでいた。
記念日なので、好きな寿司でも食べたいけれど、もちろん病院食に出てくるはずがない。母に頼んで寿司屋に買いに行ってもらったが、あいにくその日は休みだった。絵の脇に、残念な気持ちを日記のように綴った。
色は褪せてしまったが、まわりの紫色の楕円は、故郷の家から持ってきてもらったドドメ(桑の実)で、母にこすりつけてもらった。
花キリンは、同じ年の秋十月に描いた。一緒に入院していた人が、退院してから持ってきてくれた鉢植えだ。鉢植えは病室では手入れもできないし、花を枯らしてしまうことが多かったが、花キリンは、ほぼ一年中、花が終わることがなかった。退院の日まで九年間、病室で育て、今では見上げるほど大きくなり、家で元気に咲いている。
どうしてもうまく描けない日もあった。なにを描いたか、字で説明を加えるしかない。柿の右上に菊の花びらを描こうとしたが、途中で止めてしまった。その隣も、ミョウガに見えない。
「良い字も絵もかけない こんな日もいいもんだ」──
これで自分を慰めた。

星野 富弘 (ほしの とみひろ)
1946年 群馬県勢多郡東村に生まれる
1970年 群馬大学教育学部体育科卒業。中学校の教諭になるがクラブ活動の指導中頸髄を損傷、手足の自由を失う
1972年 病院に入院中、口に筆をくわえて文や絵を書き始める
1979年 前橋で最初の作品展を開く。退院
1981年 雑誌や新聞に詩画作品や、エッセイを連載
1982年 高崎で「花の詩画展」。以後、全国各地で開かれた「花の詩画展」は、大きな感動を呼ぶ
1991年 群馬県勢多郡東村(現みどり市東町)に村立富弘美術館開館
1994〜97年 ニューヨークで「花の詩画展」
2000年 ホノルルで「花の詩画展」
2001年 サンフランシスコ・ロサンゼルスで「花の詩画展」
2004年 ワルシャワ国立博物館での「花の詩画展」
2005年 (新)富弘美術館新館開館
2006年 群馬県名誉県民となる
2010年 富弘美術館開館20周年 富弘美術館の入館者600万人
2011年 群馬大学特別栄誉賞(第一回)
現在も詩画や随筆の創作を続けながら、全国で「花の詩画展」を開いている
作品紹介

怪我をして手足の自由を奪われた中で、字を書き、絵を描き始めて、ついには詩と絵を融合させた詩画という世界を確立させるまでの過程で、絵といかに向き合い、生きる希望をつないできたかを絵の変遷をたどりながら、創作への熱い思いを語りつくした1冊。
定価:1,400円+税/学研プラス
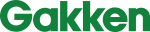

















 ページトップへ
ページトップへ