

谷原:人間はなぜ物語を必要とするんでしょうね。これは素朴な疑問なのですが。
道尾:僕も、人類初の作家は誰だったのかなって考えることがあります。原始の人間が、何かの現象と何かの現象とを、心の中で結びつけたのが始まりだと思うんですね。例えば、なんとなく手をたたいた瞬間に夜空で星が流れて、その二つの出来事を単なる偶然としてとらえず、心の中で関連づけたり。あるいは小さな星と星をつないで、何かのかたちを思い浮かべるだけでも、一つの物語ですよね。

谷原:もしかしたら人間って、現実だけじゃ生きていけないんですかね。
道尾:そうだと思います。ほとんどの人は片目をつぶって生きていて、片方のまぶたの裏にいつも物語を描いているんじゃないでしょうか。そんな中で、ときおり両目をつぶってしまう人も出てくるんだと思います。
谷原:僕はお芝居で生きているんですけど、農家のように生活に役立つものを作っているわけではない。世相が例えば戦時中のように切迫した状況になると演劇のようなエンターテイメントってまっさきに削られるものでしょう。逆にそういう時代だからこそ僕はストーリーというものが必要だと思いますが。
ただ、おなかがいくらいっぱいになってもお金がいくらあっても、心の栄養みたいなものが枯渇してしまうと、ただ人は飯を食って排泄をするだけの生き物になってしまう。心が元気に活き活きとしているためには、なんらかの物語が必要なんだと思います。僕らの俳優という職業は、観終わった人が何か元気になるとか、明日からがんばろうって思ってもらえる気持ちみたいなものを作っているのかな、なんて思うこともありますね。

道尾:ちょっと語弊がありますけど、僕は「読者のため」という気持ちでは書いてないんです。狙い定めてショーマンシップを発揮すると、小説はたしかに売れるんですけど、つまらなくなってしまう。そういった最大公約数を狙ったものを作りたくないというのがあって、僕自身が読んだときの気持ちよさのためだけに書く、ということを続けているんです。
だけど、読んだ人から救われたという一言をいただいたときは別で、それは心から嬉しいです。僕はいつも小説で「救い」を書きたいと思っているので。
でも「救い」を書くのって、すごく難しいですよね。小説は、どんなにひどい状況になっても、次の一行で何とでもできる。ものの数秒で世界全体を救うことができます。でも、そういう安易なやり方だと、読んでいる人を救うことは絶対にできないんですよね。
谷原:『ノエル』に書かれているエピソードは、自分の足で光に近づくというのが素敵ですよね。
道尾:童話がテーマということもあって、書きながら「マッチ売りの少女」を思っていました。あれは俯瞰してみると単に「お金のない女の子が街角で死んでしまいました」という話ですが、登場人物に寄り添ってみれば間違いなく救いを描いた作品ですから。
もくじ
人の感動のスイッチをいかに押さないかが作家の勝負所だと思うんですよね(道尾)
——道尾さんは、登場人物ひとりひとりの心情に寄り添って書くということを旨としておられます。自分で責任をもって心情を引き受けられなければ、どんな登場人物でも書けないと。そこは役者さんが演技をされる場合とよく似ているように思います。たとえば、谷原さんが自分が演じたいと思っている世界と脚本との間にすきまがあった場合、それはどのように埋められるのでしょうか?

谷原:できないと言うと発展しないので、どうやったらこの台詞を言えるのかな、と考えます。心の置き場所や重心を少し変えることで、その台詞が言えるようになるんですよ。自分の方に引きつけて「こうじゃないと駄目」と考えるのではなくて、「この役だったらこう言わせたほうがいいな」という風に考えます。「僕の主観」ではなく「役の主観」ですね。
道尾:そのとき意識するのは、見ているお客さんではないわけですね。
谷原:それは後ですね。背負っている役の人物がシーンごとに積み重ねてきたものを裏切らないようにします。たとえばお客さんからすれば「40分目まではよかったけど41分目のこの台詞で台無し」みたいになってしまう可能性だってあるじゃないですか。僕自身の責任において、どうやったらこの役をまっとうできるのかっていうことですよね。
脚本家やプロデューサーの方は僕らと違う視点で物語を作っているので、時として矛盾が生じるのはしょうがないんです。それを一個一個修正していったらただ辻褄があうだけでつまらなくなってしまう。だから視点を変えて、どうやったら自分の解釈で言えるようにするかとか、そう考えますね。
僕は道尾さんのようになかなかずばっとお客さんのことなんか考えてないとは言いにくいので(笑)。それは迎合しないということじゃないですよね?

道尾:そうです。僕も作家なので、人の感動のスイッチがどこにあるかくらいわかるんですよ。でもそこをいかに押さないかが作家の勝負所だと思うんですよね。流したことのない涙を流してもらうというのが大切で、せっかくものを作っているんだから、それを味わう人の中に新しい現象が起きなければ意味がないと思うんですよ。
谷原:道尾さんの作品はスタイルが毎回ちがいますよね。小説のスタイルって、今度はこれを狙ってみようという感じで決められているんでしょうか。
道尾:やりたいことはいつもたくさんあるんですけど、その中には水と油みたいに合わないものがあるんです。一つの作品を書いているときに、一方でその「合わないもの」が蓄積していって、後からそこを見てみると、不思議に統一感がとれている。それが次の作品になることが多いですね。

谷原:そういうのってどう湧いてくるんですか?
道尾:いえ、やっぱり文章にしてからです。何も浮かばないときに、まず1ページだけ書いてみたりもします。ただ男が歩いてる情景を描写しただけでも、どこから来たのか、どうして歩いてるのかという疑問が浮かんできて、さっきも言った「書かれていないことの多さ」が如実にわかってくるんですね。「男が歩いていた」と書いてあるその背景には、無数に書かれていないことがあって、それが物語の可能性なんです。だから、どんな情景でも、書くと急に楽しくなってきます。僕の場合、「何も浮かばない」って悩んでるだけじゃ絶対に物語は生まれないんですよ。

谷原:最初の一文が種みたいなもので、そこからどんどん枝葉が繁ってという感じなんですね。普段ネタ帳みたいなものをつけていたり、ということではないんですね。
道尾:これは今度使えるかなっていうのが浮かぶと一応メモしますけど、まず使えないですね(笑)。
だんだん自分のしゃべっている言葉に脳が騙されていくような感じはあるんですよ(谷原)

谷原:僕の役者という仕事だと、自分のところまで来たときにもうストーリーは出来上がっていて、自分の意見は反映されづらいです。設定はこっちのほうがいいんじゃないかと思ったとしても、出来上がってるものを変えるのはルール違反ですから。
僕らは、言ってしまえば最初にストーリーを読む視聴者に近いのではないでしょうか。だから道尾さんのようにストーリーを作る人の話を聞いてると無性に羨ましいです。
道尾:演じてる人にストーリーも作られちゃったら、我々はやることがなくなってしまいます(笑)。
谷原:たとえば映像化で、自分がつくったストーリーがこんな設定になっちゃってるとか、そういうのは気になる方ですか?

道尾:完全に別物だと思ってるので、僕自身は映像化という言葉自体も使わないようにしてるんです。映像化というより、映像版ですよね。もともと「絶対に映像化できないこと」を自分の作品の条件にしていますから、「映像化」できるものなら僕がいちばん見てみたいです(笑)。でも自分の作品の映像版は、いつも純粋に楽しんで見させていただいています。
谷原:なるほど。
道尾:そうだ、ちょっとお訊ねしたかったんです。以前、お酒の席で小林亜星さんにお聞きしたんですが、亜星さんがドラマで寺内貫太郎(※)を演じられるとき、もともとはまったく違う性格だったそうなんですよ。でも、ずっと演じていたら、自分の性格が貫太郎みたいになったとおっしゃっていて。そういうことはよく起きるものなんですか?

谷原:いろいろな方がいらっしゃるとは思うんですよ。現場に入る瞬間にオン・オフの切り替えをする方もいらっしゃいますし、千差万別ですね。ただ、役をしているときに引っぱられることはよくあります。なりきろう、なりきろうとやっていると、だんだん自分のしゃべっている言葉に脳が騙されていくような感じはあります。
道尾:僕はもちろん役者の経験はないので、自分が思ったこと以外を口にしたことが一度もないんです。自分以外の人が自分の口から何かをしゃべるわけですから、役者さんの中ではすごく不思議なことが起きてるんですね。
谷原:そうなんです。親からも「あの一言はないよ」って言われることがあるんですけど、それは台詞だし(笑)。僕らは生活していく上で、親と会ったり、恋人とあったり、というそれぞれの場合で仮面をかぶるというか、相手に影響されて自分が微妙に変化するじゃないですか。役者ではないですけど、道尾さんも他の人も少しずつ演じ分けるっていうのをやってると思うんです。
道尾:そうですね。そういうアドリブ演技をまじえながら毎日を生きているのかもしれませんね。
※寺内貫太郎:1974年にTBS系列で放映されたドラマ『寺内貫太郎一家』の主人公。東京の下町で三代続く石屋 「寺内石材店」の主人で頑固親父。短気ですぐに手が出て、ちゃぶ台をひっくり返す。
僕の趣味と、世の中の人のある程度の人数の趣味が共通してたから本が出せてるんだと思うんです(道尾)

谷原:道尾さんはいつ物語を書くのを生業にしようとおもったんですか?
道尾:決めたのは19歳のときですね。10年間かけて何かの職業になろうと頑張って、それでもなれなかったら才能が無いということだと考えて、10年で30歳になるまでやってみようと思いました。それでぎりぎり29歳のときにデビューできたんです。
谷原:自分のなかでこの一冊を読んでなろうと決めた本というのはありますか?
道尾:小説をたくさん読むようになって、若い時代特有の思い込みで、自分が書いたほうがおもしろいんじゃないかと思ったんです。で、実際やってみたら自分が書いたやつのほうがおもしろかった(笑)。
谷原:ほう(笑)。
道尾:プロの作家の作品よりも、19歳の自分が書いたものの方がおもしろいって言えるのは、世界で僕だけだったんです。僕以外の人が読んだら、書店で売られている小説のほうがおもしろいに決まってます。でも、クオリティはともかく、趣味は100%僕に合ってる小説なわけですよね。だから僕が読む限りは最高におもしろい。
それで最初の勘違いが始まって、それから19年間ずっと勘違いが続いてる状態です。僕の趣味と、世の中の人のある程度の人数の趣味が共通してたから本が出せてるんだと思うんです。

谷原:でも、19歳で俺には書けるなって思った時に、ストーリーの組立て方とか、自分なりのある程度の論理みたいなものが見えたからそう思ったわけですよね。それって小説書きの共通項みたいなものが見出だせたわけですから、勘違いじゃないんじゃないですか。
道尾:文章の持っている力の大きさが本を読むたびにわかってきて、僕ならそれをこう使うんだけどなみたいなのがあったんですね。そういう文章の用法は自分のものにできたと思うのですが、すべての人におもしろいと言わせられるようなストーリーの組み立て方は残念ながら今でもわかりません。自分がおもしろいと言えるものを書くだけですね。
(次号に続く)
作品紹介

ノエル: -a story of stories-
物語をつくってごらん。きっと、自分の望む世界が開けるからー理不尽な暴力を躱すために、絵本作りを始めた中学生の男女。妹の誕生と祖母の病で不安に陥り、絵本に救いを求める少女。最愛の妻を亡くし、生きがいを見失った老境の元教師。それぞれの切ない人生を「物語」が変えていく…どうしようもない現実に舞い降りた、奇跡のようなチェーンストーリー。最も美しく劇的な道尾マジック。
プロフィール
谷原 章介
1972年神奈川県出身。俳優。雑誌「メンズノンノ」の専属モデルから1995年映画「花より男子」でデビュー。二枚目から三枚目まで幅広い役柄を演じる。またTBS「王様のブランチ」NHK「きょうの料理」の司会者としても活躍中。2014年NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」に竹中半兵衛役で出演が決定。
道尾 秀介
1975年東京都出身。2004年、「背の眼」でホラーサスペンス大賞特別賞を受賞し、作家としてデビュー。2007年「シャドウ」で本格ミステリ大賞、2009年「カラスの親指」で日本推理作家協会賞、2010年「龍神の雨」で大藪春彦賞、「光媒の花」で山本周五郎賞を受賞。2011年「月と蟹」で直木賞を受賞。近著に「カササギたちの四季」「水の柩」「光」「ノエル」「笑うハーレキン」などがある。
バックナンバー
- 第1回 第一話を書くときには登場人物たちの運命がどうなるかはまったくわからない(道尾)
- 第3回 デスメタルとの違いは、サビがあることでしょうね。僕はやっぱりサビがあるのが好きなんです、小説でも(道尾)
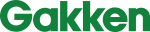
















 ページトップへ
ページトップへ